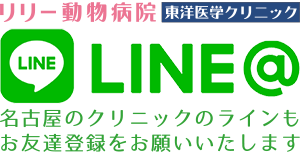ちょっとしたお話
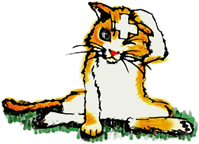
ここのところ、ひと月~ふた月くらいの間に、猫の外傷でお見えになる方が増えています。
その外傷で通院なさっているYさんという飼い主さん(この方はご自分の猫が二匹いるのにも拘らず、野良猫6~7匹のお世話をしてみえる奇特な方です!)と先日お話しをした時の事です。
- 私 「もしかしたら、猫の発情と関係あるのかないのか・・・本当に最近猫ちゃんの外傷がすごく多いんですよね~・・・。」
- Yさん 「そうだよね~・・・。やっぱ女の子の取り合いをするのかな~・・・??よくよく考えたら、猫の出産って、春が多いから、今の時期は発情の関係で喧嘩が多いんだろうね~・・・。。。」
・・・ホントそうだと思います。(まぁ、でもオス猫はやはりテリトリー意識が強いが故に、去勢したオス猫ちゃんも年中喧嘩はしてますが・・。)
特に外に出す猫ちゃんは喧嘩が多く、そして、よっぽど酷くならない限り、家で症状を出しません。
飼い主さんが気付かれた時には、痛みと敗血症の一歩手前で「食欲が落ちた。」とか、「身体から悪臭のする膿を出している!」という凛告(りんこく)でお見えになることが殆どです。
そういう患者さんがお見えになったら、まず膿の培養検査をします。(外注です)
そして、うちにある抗生物質でどれが効くかを判定します。
ただ、その結果が出るまでに時間(喧嘩による咬傷時に細菌感染によって出来てしまった膿を少し取って育てて、何が原因菌であるかを調べるのに掛かる時間のことです。)が掛かりますので、取り敢えず広範囲の細菌を叩くことの出来る抗生物質を二種類選んで注射して様子を見ます。
症状によっては、内服薬でよくなる子もいれば、抗生物質で細菌のコントロールをした後、外科手術をしなくてはならない子もいます。(結構います!)
病院に連れてこられる飼い主さんは、当たり前の話になりますが、ご自分の猫ちゃんを可愛がってみえる方が殆どなので、その度飼い主さんと私達は「あ~・・・・。こんなに酷くなっちゃってたのね~・・。お口が利けたらもっと早くに分かったのにね~・・・。」と言う会話を交わします。
数日経つと、原因菌の培養結果とそれに合う抗生物質が割り出されるので、もし合わなければ別の抗生物質をお出しするなり、合っているようでしたら更に同じ抗生物質で数日間様子を見て頂きます。
あまり参考にならないでしょうが、当院で最近出た細菌は(ダジャレみたいですが。)スタフィロコッカスとG型溶血連鎖球菌、そしてフソバクテリウム属の菌でした。
以前から、猫の飼い主さんに 「猫は自由が好きだと言う気持ちを尊重して、外に出すことにより、感染るかもしれない病気や喧嘩での外傷もこれもこの子の運命だとして受け止めるか・・・、はたまた猫の自由は奪うけど、安全を取るか・・・。どちからの選択だと思います。」とお話しています。
もし、前者の方がお見えになられましたら、一日一回は必ず頭の先からシッポの先まで触ってみて、痛がらないか?出血や膿のような物が出ていないかをチェックしてくださいね!
 今日は、ワクチンで予防できる猫ちゃんの伝染病についてご紹介します。
今日は、ワクチンで予防できる猫ちゃんの伝染病についてご紹介します。
当院では猫ちゃんのワクチンの種類として、3種と4種を用意しております。
3種で予防できるのは、「猫ウイルス性鼻気管炎・猫カリシウイルス感染症・猫汎白血球減少症」の3種類の伝染病です。
4種の場合、これに「猫白血病」が加わります。いずれの病気も伝染力が強く、感染猫の唾液や鼻水・目ヤニなどから感染します。
それでは、ひとつずつご紹介します。
- 猫ウイルス性鼻気管炎
猫ヘルペスウイルスによっておこる病気で、40℃前後の発熱と激しいクシャミ・咳を示し多量の鼻水や目ヤニがでます。
また他のウイルスや細菌との混合感染を引き起こして、重い症状となって死亡することもあります。
特に子猫のときはかかりやすく、高い死亡率を示す場合もあります。 - 猫カリシウイルス感染症
猫ウイルス性鼻気管炎と類似のカゼ様症状を示しますが、進行すると口の中や舌に水疱や潰瘍をつくります。
一般的に鼻気管炎よりは軽い症状ですが、混合感染する場合が多く、この場合は重い症状となります。 - 猫汎白血球減少症(別名:猫伝染性腸炎)
パルボウイルスによる病気で、高熱、嘔吐、下痢などの症状を示し、血液中の白血球の数が著しく少なくなります。
脱水症状がつづくと猫は衰弱し、特に子猫では非常に死亡率の高い伝染病です。 - 猫白血病
猫白血病ウイルスに感染すると、はじめは健康そうに見えますが、次第に元気がなくなっていきます。
免疫力が低下するので、あらゆる感染症に抵抗できない状態になり、口内炎、胃腸炎、鼻炎などがなかなか治らず、またリンパ腫や白血病など致命的な病気を伴い最後は高確率で死んでしまう病気です。
感染猫の唾液には多くのウイルスが含まれていて、猫同士の毛づくろいなどをつうじて口、鼻から感染します。
また、お母さんが感染していると、その赤ちゃんにも感染が伝搬することが多い病気です。
猫ちゃんのワクチンは、8週齢くらいから接種が可能です。始めの年だけ、間隔をあけての2回接種が必要で、その次の年からは、1回ずつ1年ごとに追加接種が必要です。
猫ちゃんがこれらの伝染病にかからないように、または症状の発現を最小限にできるように、毎年のワクチン接種をお勧めします。
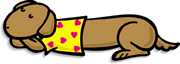 今回は、胴が長くて腰に負担のかかりやすいダックスさんやコーギーさんに多い病気、椎間板ヘルニアについてお話します。
今回は、胴が長くて腰に負担のかかりやすいダックスさんやコーギーさんに多い病気、椎間板ヘルニアについてお話します。
椎間板というのは、背骨を構成する骨と骨の間のクッションのような役割を果たしているものです。
椎間板は椎体と椎体の間に通常はきれいに収まっているのですが、なんらかの原因によって外に飛び出して背骨の神経を圧迫し、さまざまな障害を引き起こすことがあります。
<要因>
成長期の急激な体格の変化の他、肥満や痩せすぎ、過激な運動などによって、ひずみが生じ、それが背骨への負担となります。
高い場所から飛び降りたりすることも、背骨に負担をかける原因になります。
<主な症状>
歩き方がおかしい、抱いたり背中を触ったりすると痛がる、立ち上がり方が緩慢、などが初期症状です。
ヘルニアは放っておくとどんどん悪化してしまう病気で、重症になってくると、下肢が麻痺して歩けなくなってしまう状態になります。
<治療>
初期段階であれば手術する必要はなく、抗炎症剤と安静によって回復する場合があります。
針灸も効果的です。また、再発をふせぐための体重や運動のコントロールも大切です。
手術の場合は、飛び出た椎間板そのものを取り除く方法や、神経を圧迫する骨を削る方法があります。
重度の急性症状の場合、早く手術しないと一生歩けなくなる可能性が高いとも言われています。
早期発見、早期治療が大切な病気なので、飼い主さんの、普段からの注意と観察が大切です。
もし疑わしい症状が見られたら、すぐに受診されることをお勧めします。
 ますます寒くなってきましたね。
ますます寒くなってきましたね。
冬の季節は動物たちも飲水量が減り、膀胱に濃い尿がたまりがちなせいか、膀胱炎や膀胱結石・尿道結石を患ってしまうワンちゃんや猫ちゃんが多いように思います。
次のようなサインが見られたら要注意です…!
お早めにご来院下さい。
- おしっこの回数が増えた・トイレにいく回数が増えた
- しようとするがおしっこが出ない
- おしっこをするときに痛そう
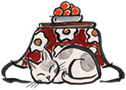 膀胱炎になると残尿感があるので、トイレの回数が増えます。また、血尿が出たりします。
膀胱炎になると残尿感があるので、トイレの回数が増えます。また、血尿が出たりします。
尿道に結石がつまってしまった場合は、ワンちゃん・猫ちゃんはおしっこを出したくても出せない状態なのですが、これは放っておいて1日や2日がたつと、膀胱にたまった尿の毒素が急性に腎臓を侵し、次には体全体にまわってしまい、「尿毒症」という危険な状態になってしまいます。
こうなると元気も食欲もなくなり、嘔吐などの症状が見られます。
こうなる前に、飼い主さんの普段からの動物たちのおしっこの出具合や状態の観察が大事になります。
これらの病気のおうちでできる予防法としては、やはり水分をいっぱい摂らせてあげることです。
なかなかお水を飲まないこの場合は、肉のゆで汁やだし汁をあげたり、普段のゴハンをふやかしてあげたり、スポイトでお水を飲ませてあげるのも工夫のひとつです。
また、まめにお散歩をしておしっこをがまんさせないようにするのも、予防のひとつです。
 だんだん寒くなってきましたね。急な冷え込みに、体調を崩したりしていませんか?
だんだん寒くなってきましたね。急な冷え込みに、体調を崩したりしていませんか?
この時期は人間同様、動物たちも体調を崩しやすい時期と言えます。今回はそんな冬場に多い病気のひとつー気管支炎についてのお話です。
冬は空気が冷たく乾いているので、気道粘膜のバリア機能が弱まり、外からの刺激を受けやすい状態にあります。
そのため、口から侵入したウイルスや細菌によって容易に炎症を起こしやすくなっている状態にあります。
こうしてなってしまう病気が、気管支炎です。
<気管支炎の症状>
- 呼吸が浅く、速い
- 呼吸が苦しそう
- 咳をする、のどになにか突っかかったようなしぐさをする
<病院での治療法>
- 炎症を抑えるお薬や、気道を広げるお薬、吸入療法などで治療をします。
<おうちでできる予防法>
- 加湿器の使用や、ぬれたタオルなどの室内干しで、加湿をこころがけてあげる。
- 屋外のコの場合は、風除けを置くなどして冷気を防いであげる。
気管支炎は、進行すると肺炎や肺水腫になって、命に関わってくることもある病気です。
もし症状が見られたら、進行してしまわないうちに診察にいらしてくださいね。
 今回は、動物たちのサプリメントのご紹介です。
今回は、動物たちのサプリメントのご紹介です。
人間同様動物たちにも、健康を助けるサプリメントがいろいろあります‥!
今回は、その中でも特に当院でお出しすることが多いサプリメントを4つ、ご紹介します。
マコモ
水辺のイネ科植物「マコモ」の粉です。
マコモには、解毒作用や血液・体液の浄化作用(デトックス作用)、免疫力増加作用があるといわれ、皮膚病や傷、やけどに塗ったり、実際にマコモを飲むことで効果が期待されます。
動物たちだけでなく、院長も愛飲している一品です。
R&U
もとは麹(こうじ)の一種から抽出した、生理活性物質「RU」です。
体内のホルモン活性を促すことにより、「生体が正常な生理作用を営む」という作用をもっています。
多くの皮膚病に対しての有効性も報告されており、皮膚疾患や高齢化対策のサプリメントとして活躍しています。
また、RUが配合されたR&Uシャンプーもあります。
ベジタブルサポート
栄養価の高いカボチャ、ブロッコリー、にんじん、シイタケの粉を、吸収しやすいように「高速低温粉砕」した、野菜の粉です。天然素材だけを使用しています。
アミノ酸バランスが良く、肝臓でのタンパク合成能力を上昇させるのに役立ちます。また、消化機能がおちている高齢犬のコのごはんに、栄養補助として加えてあげるのもお勧めです。
DHA
青魚に多く含まれる不飽和脂肪酸「ドコサヘキサエン酸」の略です。
脳の神経を活性化する働きがあり、ワンちゃんの場合は夜鳴きや回転運動といった、痴呆の予防や改善に効くサプリメントです。
また、中性脂肪の低下や、アトピー性皮膚炎の改善、視力の回復にも効果があるといわれています。
興味のあるかたはご来院の際、お気軽におっしゃってくださいね。
今回はわんちゃん、猫ちゃんの年をとったらなりやすくなる病気について、ほんの一部ですがご紹介します。
【女の子がなる病気】
・乳腺腫瘍
おっぱいの周辺にしこりのようなものができます。わんちゃんの場合は50%が悪性のもので、猫ちゃんの場合は90%が悪性のものといわれています。
手術で取り除きますが、悪性だとすでに肺やリンパ節に転移していたり、再発することもあります。予防としては、若いうちの避妊手術です。(具体的なことついては避妊手術のお話をお読みください。)
・子宮蓄膿症
子宮で細菌感染がおこって化膿し、膿がたまってしまう病気です。症状としては、多飲多尿や食欲不振、嘔吐、膣から膿が出るといった症状です。
そのままにしていたら体中に毒がまわり確実に死んでしまう病気で、発見されたら緊急手術で子宮を摘出します。これも予防として若いうちの避妊手術をお勧めしています。
【男の子がなる病気】
・前立腺肥大
膀胱の出口近くにある前立腺(オスの精液の成分のひとつを作り出す生殖器官)が肥大してくる病気です。
症状としては肥大した前立腺の圧迫による排便排尿困難が見られます。男性ホルモンが関わる病気なので予防や治療としては、去勢手術となります。
【小型犬に多い病気】
・僧帽弁閉鎖不全症
心臓の四つに分かれてる部屋の内の、左上の部屋(左心房)と左下の部屋(左心室)の間をつなぐフタである「僧帽弁」が、完全に閉じなくなり、血液が逆流します。初期は無症状ですが、血液の逆流がひどくなると全身に血液を送るのが難しくなり、疲れやすいといった様子や、咳などの症状が見られます。
進行性の病気ですが、血管拡張剤で心臓の負担を減らすなどの対処療法で、長期にわたって維持できます。
【胴長のこ(ダックスさんなど)がなりやすい病気】
・椎間板ヘルニア
背骨の椎間板物質が、上の神経に圧迫を加えることによって発症する病気で、背骨を触られると痛がったり、階段を昇るのを嫌がる、といった症状が見られます。
症状が軽い場合は副腎皮質ホルモンを投与して、絶対安静が必要となります。重い場合、圧迫を手術で取り除くこともあります。
【猫ちゃんに多い病気(わんちゃんでも起こります)】
・腎不全
腎臓機能が極端に低下して、正常に働かなくなってしまう病気です。急性と慢性があり、特に慢性腎不全は老齢の猫ちゃんがなりやすい病気です。
症状としては初めに多飲多尿が見られ、うすいおしっこが見られます。次に嘔吐や食欲不振が見られるようになり、末期症状では尿が出なくなってしまい、尿毒症(尿から出せない老廃物が全身をまわってしまう状態)になって亡くなってしまいます。
早期発見によって進行をおさえられる病気なので、定期的な尿と血液の検査をお勧めします。

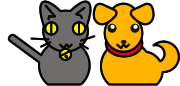 まだ残暑がつづく中、みなさんいかがお過ごしですか?
まだ残暑がつづく中、みなさんいかがお過ごしですか?
以前に犬と猫の避妊手術についてのお話を掲載したので、今回は去勢手術についてのお話を、簡単にさせていただきます。
1.手術のタイミングは?
女の子の避妊同様、性成熟の前の6~9ヶ月前後が望ましいと言われています。
特に睾丸(精巣)がちゃんと下降せずにお腹の中に残っている、いわゆる「陰睾(*)」の子の場合、精巣が腫瘍化する可能性が普通の子よりも何倍も高くなるので、早めの去勢手術をお勧めしています。
(*)陰睾とは…
犬と猫の精巣は、生まれた直後はまだお腹の中にあるのですが、生後数ヶ月以内に鼠径部(内股の部分)を通って下降してきて、陰嚢内に収まります。
「陰睾」はこの下降が正常におこらず、精巣がお腹の中か鼠径部に停留してしまっている状態をいいます。
この場合精巣は陰嚢内よりも温度が高い環境にさらされるので、正常な機能を営めません。
2.メリットは?
-
病気にかかりにくくなる
高齢になるとなりやすい前立腺の病気や、精巣・肛門周辺の腫瘍の予防、会陰ヘルニア(肛門近くの筋肉が弱くなり、そこから直腸や膀胱が筋肉の外にとびだしてきてしまう病気)の予防になります。 -
問題行動が減る
マーキング(排尿によるテリトリーの主張)や支配性による攻撃、ほかのオスとの争いといった行動を起こす可能性がぐんと低くなります。 -
メス犬・猫を気にせずにすむ
メスの子に望まない妊娠をさせてしまう可能性がなくなります。
3.デメリットは?
-
交配できなくなる
精巣を除去してしまうため、精子を産生することができなくなり、交配が不可能になります。 -
太りやすくなることがある
エネルギーの代謝に変化が起こるためか、女の子の避妊後と同様、太りやすくなる子がいます。
以上、去勢手術についてお話させていただきました。睾丸をとってしまうこと、麻酔をかけること、いろいろ悩まれることはあると思いますが、やはり病気予防の意味では、手術をお勧めしています。
交配の予定などよくご家族で話し合って、判断なさってくださいね。
 知られているようで、意外と知られてないのが、肛門嚢炎と肛門周囲ろう孔です。
知られているようで、意外と知られてないのが、肛門嚢炎と肛門周囲ろう孔です。
<肛門嚢炎>
犬や猫は、スカンクの様に肛門の両脇に悪臭を放つ、一対の袋状の肛門嚢という分泌腺を持っています。
肛門嚢の内容物は、通常排便の時にいきむと、便と一緒にその開口部から排出されます。
肛門周囲は、常に便や泥などで汚染されていて、病気をおこしやすい環境下にあります。
この肛門嚢が細菌感染を受けたり、導管(嚢にある内容物の出口)が塞がってしまったりすると、嚢内は化膿した膿汁で満たされ、やがて肛門嚢炎になります。
更に進行すると、次第に化膿巣が肛門周囲に広がっていきます。
これを放置しておくと、いずれ肛門嚢の一部が破れてきて痛みを伴い、その創口から膿汁が排出されることがあります。
症状は、痛みなどの不快感、すなわち肛門部を舐める、咬む、または肛門部を床につけて歩く、独特の動作をしたりします。
そして進行と共に、食欲の低下、発熱などが起こり、肛門嚢の皮膚が破れてくると、上に書いた通り、膿汁の排泄や出血が起こります。
<肛門周囲ろう孔>
基本的には、肛門嚢炎の延長線上にあると考えて頂いて間違いではないと思います。
また肛門嚢炎から進行する形だけではなく、肛門周囲の汗腺や毛包に細菌感染が起こり、皮膚炎となり、それが進行して膿瘍が形成されることから起こることもあります。
その皮膚炎が膿瘍を形成して、やがて皮膚に穴が開くのですが(化膿性ろう孔)重度になると、その穴が多数開口し、各々がアリの巣状に繋がるようになります。
その状態が更に進行すると、ろう孔は皮下組織、筋肉へと深部にまで及び、直腸や腹腔にまで達するようになります。
症状は肛門嚢炎とほぼ同じですが、排便困難や便秘、下痢、あるいは便の失禁などを呈し、やがて食欲不振や発熱などになる動物もいます。
<治療>
 肛門嚢炎に関しては、初期でしたら、たまった肛門嚢の内容物を排出させると同時に内服薬や外用薬の投与で治癒することもあります。
肛門嚢炎に関しては、初期でしたら、たまった肛門嚢の内容物を排出させると同時に内服薬や外用薬の投与で治癒することもあります。
しかし皮膚が破れて化膿した膿汁が出ている場合は、創口からの洗浄と消毒が必要になってきます。
肛門ろう孔に関しては、程度によっては外科的処置により、壊死(炎症が進んで細胞が死んだ状態)した組織を切除しなくてはならない事があります。
ただ、手術後に便失禁や肛門狭窄を起したり、肛門ろう孔を再発する場合もあります。
<予防>
いずれにせよ、動物に上の症状が起きてないかよく観察する必要があります。
また、初期であれば肛門部を床に擦り付ける仕草をする時は、肛門嚢炎におちいる一歩手前であり、導管(嚢にある内容物の出口)がつまっている為にうまく排出されていなくて、分泌物が溜まっているだけの時がよくあります。
そのような時は、肛門にティッシュを当てて、肛門嚢の内容物を搾り出すようにして排出させることにより、肛門嚢炎の予防が出来ます。
もしご自分で出来ないような時は、掛かり付けの獣医師(もしくはトリマーさん)に依頼するか、先の事を考えてご自分で出来るように搾り方を教えてもらってください。
因みに、肛門嚢の内容物は一般的には排便時に出るのですが、導管が塞がりがちな子達や肛門括約筋が低下していて、排便時に排出でき難い子達に関しては、月に一度の肛門嚢の排出をお薦めしています。
本格的な暑さになって参りました。飼い主さん共々、ワンちゃん、猫ちゃんたちは夏バテ大丈夫ですか??
今回はこんな季節には特に多い病気、外耳炎のお話です。
外耳炎というのは、簡単にいえば耳の穴に炎症がおこる病気です。
原因はいろいろありますが、外耳道に蓄積した耳垢に、細菌やカビ、酵母が繁殖して、耳道の粘膜に感染が起こるのが一般的です。
特にこの暑い季節はお耳の中の環境が悪くなりやすいので、菌が増殖するにはもってこいの状態になってしまいがちです。
特にお耳が垂れているコや耳の中に毛が生えているコは、耳の中への通気性が悪いので、外耳炎になりやすい傾向があります。
その他にも外耳炎は、耳ダニというダニが耳の中に寄生することによって起こるものや、アレルギーの症状のひとつとして起こるものもあります。
- ・耳の汚れがひどい
- ・耳を引っかく
- ・頭をしきりに振る
- ・耳がにおう
- ・首を傾けている
などなどです。
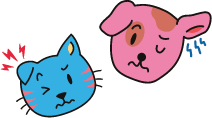
もしおうちのワンちゃん猫ちゃんにこのような症状が見られたら、外耳炎の可能性が高いです。
外耳炎の治療としてはまず原因を突き止めて、主にお耳のケアと点耳薬による治療を行います。
症状によって飲み薬を併用することもあります。アレルギーによるものが疑われる場合は、食事の変更や、アレルギー検査を行うこともあります。
外耳炎は進行してしまうと、炎症で壁が肥厚して耳の穴をふさいでしまったり、さらに奥に進行して中耳炎や内耳炎にまでなってしまう可能性もあるので、要注意です。
症状が見られたら、その段階ですぐ病院に連れて行って、炎症が軽い段階で治療を受けられることをお勧めします。